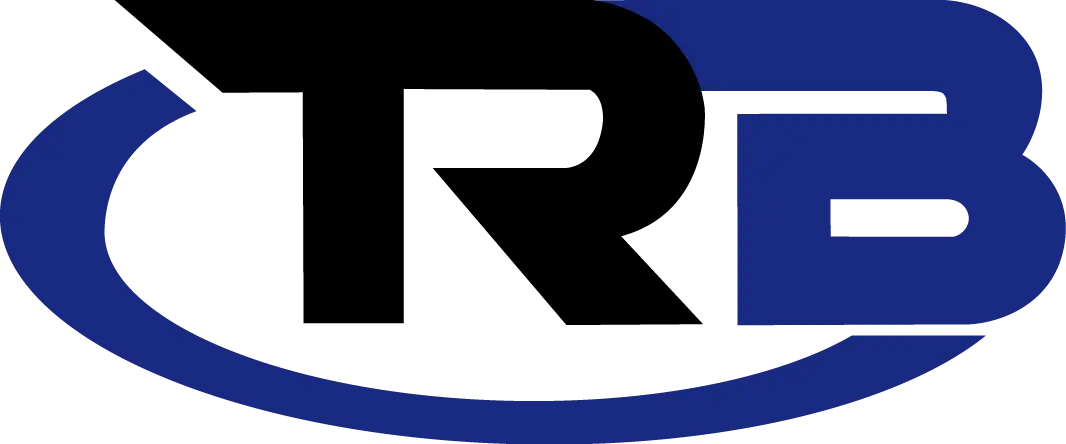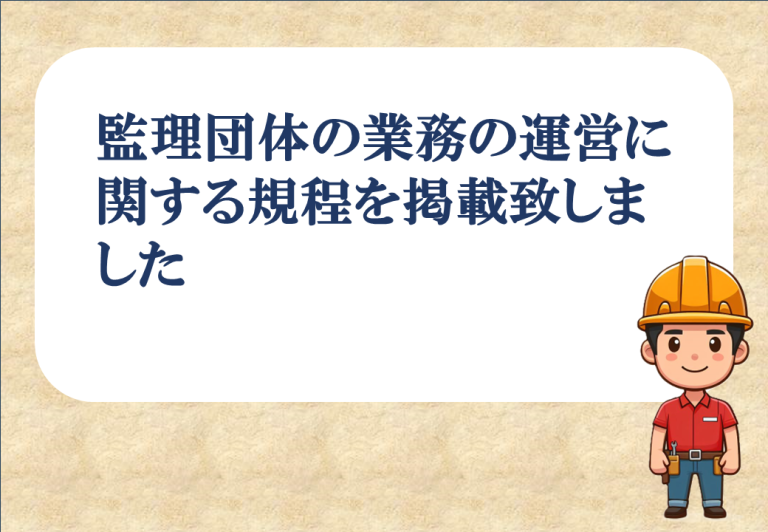育成就労制度と技能実習制度の違いについて
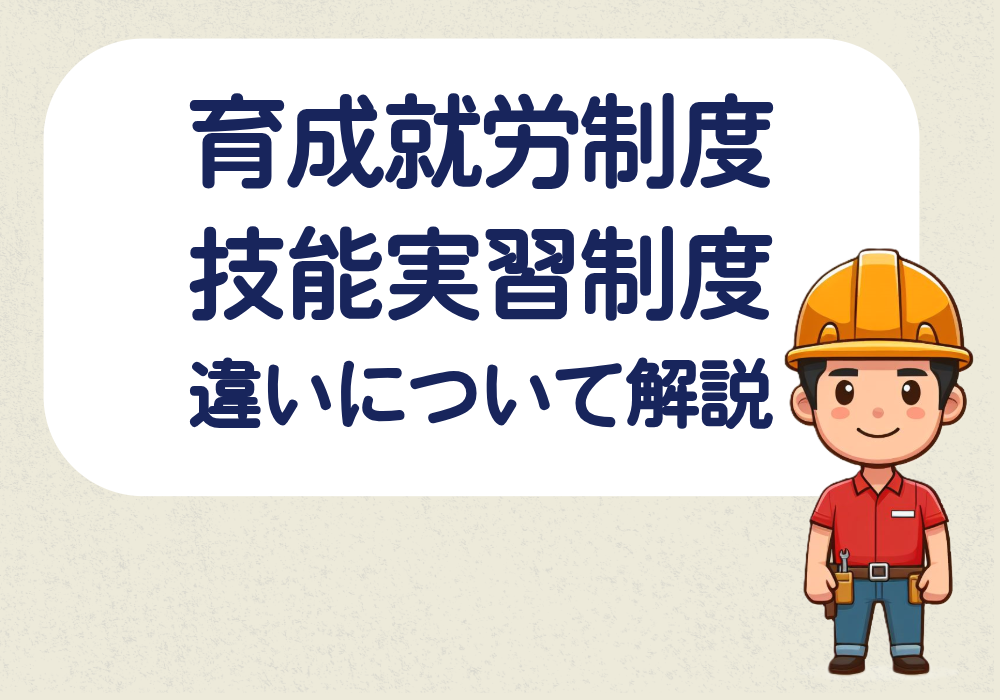
育成就労制度の概要
育成就労制度とは?
育成就労制度は、現行の技能実習制度(※技能実習制度とは?)に代わる新たな外国人雇用の制度です。2024年3月現在時点で検討が進められています。 従来の技能実習制度が国際貢献人材育成を目的としていたのに対し、新制度である「育成就労」制度は、人材確保と人材育成を目的としており、基本的に3年間の育成期間で特定技能1号(※特定技能制度とは?)の水準の人材に育成するとしています。
育成就労制度の背景と目的
- 日本の労働力不足が深刻化している中で、特に技術や技能を要する産業や職種における人材確保の課題が顕在化しています。これは、日本の人口減少や高齢化が進行する中で、ますます深刻化しています。
- 近年日本は近隣諸国との間で人材確保において競争が激化しています。台湾や韓国などの国々が、就業先としての魅力で上位に位置し、日本の相対的な魅力が低下している現状があります。このような状況下で、外国人労働者を積極的に受け入れ、労働力を補う必要性が高まり、それが制度の背景となっています。
- 技能実習制度の見直しの一環として育成就労制度の導入により、外国人労働者のスキル向上とキャリア形成を支援し、日本での長期的な就労を促進することを目的としています。外国人労働者が安心して働き、学び、生活できる環境を提供することで、国際的な人材市場で競争力を保ちつつ、国内産業の人手不足を解消する狙いがあります。
受入れ対象分野・職種について
育成就労制度の受け入れ対象分野は、国内における就労を通じた人材育成に適した分野に限定されています。 育成就労制度は、育成期間を経て特定技能1号への移行を目指す制度で、特定技能で受け入れできる職種は同じ職種になる見込みです。したがって、外国人労働者が従事できる業務の範囲は移行先の制度である「特定技能制度の設定分野」に限定されます。そのため、既存の技能実習制度とは異なり、特定の業界や分野において大幅な変更が発生する可能性があります。
育成就労制度と技能実習制度の比較
比較表
以下に、育成就労制度と技能実習制度の主要な項目について比較し、それぞれの特徴と違いを明確にします。
| 項目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |
| ① 目的 | 外国人材の育成、外国人材確保 | 外国人材育成、国際貢献 |
| ② 在留期間 | 3年(原則) | 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)➡通算5年間 |
| ③ 在留資格取得要件 | 受入前の段階で日本語能力試験N5等(原則) | 原則なし(介護は日本語能力試験N4等) |
| ④ 受入対象分野 | 特定技能と同じ分野になる予定である(12分野) | 88職種・161作業 |
| ⑤ 転籍(転職) | 所定の条件を満たせば可 | 基本的に不可 |
| ⑥ 受入れ人数枠 | 分野ごとの上限があり | 受入企業の常勤職員の人数による |
これらの制度は目的や運用方法に違いがあり、それぞれの特徴を明確になりました。育成就労制度の大きな特徴として、転籍が一定の要件の下で認められる点が挙げられます。
育成就労制度のメリット
- 長期雇用が可能:技能実習制度と特定技能の業務内容の違いにより、在留資格の移行には整合性の調整が必要でしたが、育成就労制度では特定技能の12分野に適した職種に従事する予定で、在留資格の移行がスムーズになり、同一職種での長期雇用が可能です。これにより、企業は海外人材に対して長期的なキャリアパスを提示できるようになります。
- 日本語能力が備わった人材の採用が可能:技能実習制度では日本語能力の水準が設定されておらず、職場でのコミュニケーションに課題がありました。育成就労制度では、日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5など)の合格または日本語講習の受講が必要です。これにより、日本語能力向上が促進され、企業はより円滑なコミュニケーションとスムーズな業務遂行が期待できます。特に対人サービスが主な分野では、日本語能力の向上は大きなメリットとなります。
育成就労制度の課題
- 負担費用の損失が発生する可能性:技能実習制度では転籍や転職が原則として認められていないため、受け入れ企業は初期費用を負担した上で、最大5年間同一企業での実習が行われます。育成就労制度では転籍や転職が認められるため、初期費用を負担した企業が早期に転籍された場合、費用が無駄になる可能性があります。初期費用等について、転籍先の企業が転籍前の企業に対して適切な補償を行う制度も検討されています。
- 地方における人手不足の深刻化:新制度により転籍が可能になると、最低賃金の差などから都市部での高賃金やより優遇された待遇を求めて転籍する傾向が予想されます。地方で活躍していた実習生が都市部に流出する可能性が高まり、地方での人材不足が深刻化する恐れがあります。
新制度の詳細は未だ検討段階にありますが、今後具体的な内容が報告される予定です。当組合においても、新制度の情報を随時更新し、お届けしていきます。